 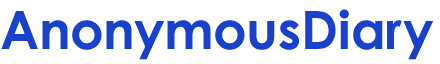 |
はてなキーワード: 後継者とは
「現場の若手芸人たちの面倒を見ている兄貴分」みたいなポジションって千鳥が引き継いだんじゃね?
トップクラスのお笑いコンビで目立ってるのってたいていツッコミのほうだけど、
千鳥の場合、ノブはMCやったりしてるけど、常に存在感があるのは大悟のほう。
それってダウンタウンと同じ構図じゃん。
売れてるツッコミってだいたいキツくなりすぎる。
くりぃむ上田とかバナナマン設楽とかオードリー若林とかハライチ岩井とかさ。
今の千鳥の「兄貴分」みたいな感じってボケの大悟が中心だからだと思うんだよな。
バカなだけのボケだとそういうふうにはなれなくて、ちゃんと主体性を持って面白いことが言えるボケ、というのが強い。
それこそがダウンタウンの、特に松本人志の後継者に必要な素養なんじゃあるまいか。
ハライチ岩井ってボケなんか。ロンブー淳と同じタイプなんやね。ネタではボケだけどトークではツッコミ気質だからそう見られるっていう。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.cinematoday.jp/news/N0143052
そもそも宮崎と高畑のためのスタジオだ~黒澤明やスタンリー・キューブリック後継者なんていないとかいつものコメントが上がってるけど
あのな確かにラピュタからジブリ立ち上げてトトロまでは宮崎と高畑のためのスタジオだったんだよ。
宮崎がまだ売れてない頃に用意してた企画がトトロまでで、トトロ終わったら宮崎はジブリは解散するつもりだった。
でもそれはもったいないって鈴木が止めて、その時の宮崎の条件で【スタッフを正社員化する】ことになってそれ以降話が変わってくるんだよ。
これは社員の生活に責任を持つってことなんだから、アーティストぶって作りたいときに作って飽きたら引退するなんてありえないんだよ。
ここらへんのいきさつも人を雇う覚悟も宮崎がインタビューで語ってたことだろ。
だからジブリで演出家育成の試験やったり外部から望月、細田、森田って優秀な演出家を呼び寄せて撮らせてたのになんでそれを無かったことにしてんだよ。
今回身内の吾郎が世代交代失敗したって言ってんのに知ったかぶった奴らがいつものコメント残すだろ?
こいつらなにがしたいんだ?
どうもこんにちは!
じいちゃんばあちゃん若返る の第一話を見て、どうしても突っ込みたいところを突っ込むので気が向いた人だけ読んでくれ。
漫画の方は今後買う予定だけど今月クレカの支払いがヤバいので来月以降の予定。
ちなみにこれは「こう書かなきゃ行けない」という話では無く、興味を持ってくれた人により深く楽しんでもらうための解説であるからして、そのつもりでひとつよろしく。
りんごは高木にあたるので、そのままにしておくと凄く大木になってしまう。すると作業性が著しく悪くなる。剪定、収穫、防除が難しくなる。
また、日の光が均等にかからないとまずいので、背が高くならないように、また横に向かって伸ばすように育てる。
そのため、上から見ると、枝が放射状に横に向かってにょろにょろと手を出すように広がっていく。
ただし、こうするとりんごの実がることによって枝が折れたりする。それを木の棒で支えている。これも作中で描かれているね。
じいさんばあさんが昔植えたという、そして黄金りんごを実らせた木がこれにあたる。古木に多い。
一方で、作中には、並木状になっているりんごの木があったと思う。これを「矮化栽培」という育て方だ。
先ほど言ったように、りんごというのはそのまま置いておくと大木になる。またコントロールが難しい。そこで、わざと大きくならないりんごの木を作って、それを高密度に植える育て方、それが矮化栽培だ。
りんごに限らず果樹は基本接ぎ木苗である。根っこの部分には生命力と根が強い木を台木にし、更にその上に目的の木を接ぎ木する。通常はそれだけなのだが、そのままでは大木になる。
そこで、根っこの台木の上に、一度矮台という大きくならない木を間に挟んで、更にその上に目的の品種を継いだ特殊な苗を使う。これを矮化栽培という。これによって木が大きくならずに育てる事ができる。
のだが、しかしこの矮化栽培も、だんだんと木が大きくなってきて、旧来型の丸木栽培に近くなっていく。こうして、並木のように並んでいる大きなりんごの木ができる。
じいさんばあさんは戦中派なので、最低でも90歳オーバーであることを考えると、ちょうどこの矮化栽培の普及時期に開拓をしていると思われる。
若返ったので、今後、じいさんばあさんは改植を進めていくものと思われる。
大きくなった矮化栽培は、矮化栽培のメリットがほぼ無くなる上に、丸木栽培よりも高密度なので丸木栽培のメリットも無い。と言う事で、通常は一定より大きくなったら切り倒してしまって、新しい苗を植える。この時に最新の品種を取り入れたりする。これを改植と言って、果樹農家は基本的に絶えず行っていく。
のだが、改植すると当然一時的に収入が減る。また高齢になってくるとなかなか未来の事を考えて行動するということができにくくなってきて、改植が進まない。
そこで、じいさんばあさんは大きくなった矮化の木を残していた(矮化栽培は枝を支える手を使うレベルまで育てるのは育てすぎ)と思われる。
が、若返ったので、この後は矮化栽培を進めていくと思われる。
さて、今の時代は、更に進んだ栽培方法がある。じいさんばあさんは、日本でりんご栽培が本格化するところ、その近代化を担ってきた世代である。当時最先端の技術を使ったベンチャー企業みたいなものだ。そう言う精神を持っている2人なので、今後は新しいことを入れていくと思われる。例えば以下の様な栽培方法がある
まず、OP 果樹農家が使うのは三脚なのだが、これが脚立になっているのは、おそらく参考になる品物が近くになかったからかな。
基本的に果樹農家が使うのは三脚である。足が多い方が安定するように思うかもしれないが、三脚の場合は3本目の足の位置を調整することで下が安定していない坂などでも安全に安定させる事ができると言う特徴がある。これが脚立の3本足だと、一本が浮いてしまうのだ。
日本では、伝統的に平坦な場所はコメまたは麦を育てる場所として使われる。そのため、果樹園は傾斜地にある事が多いのである。
りんごの栽培が本格化したのはここ150年ほどで、更に言うと戦後である。戦争から引き上げてきた人々が、食っていくために開拓をした土地にりんごを植えた所から本格化している。
日本の農業は米を重視していて、それに適した所はほぼ開拓されていた。その残りと言うのは、傾斜地で水がなかったりとするところである。そこを開拓した所だ。
じいさんばあさんは戦中に生まれ、若い時期を戦後の混乱期を過ごした人たちなので、恐らく先祖伝来の土地よりも、自分たちで開拓した土地の方が多いと思われる。
ただ、聞くところによると、2人とも元々地元の豪農の生まれらしいので、そういう点ではあるのかもしれない。
全国から考えると比較的収益性が高く後継者も多い優良な事例が多い。また、じいさんばあさんは最低でも90歳と考えると、恐らく息子さんは定年直前ぐらいではにだろうか。
一緒に暮らそう、と言うよりも、どちらかというと定年帰農を考える話になっていくのが現実によくある話だと思う。
そうすると話が複雑になってしまうので、省略されたのだと思う。
うちの会社では社員恋愛にも社員同士の結婚も何も言わないけど、長年「子供が生まれたら女性は退職」というルールは守ってもらっていた。
その代わり、子供のいる社員には大手企業以上に様々な名目で手当てを支給してきた。
これは会社のためでもなく、社員のためでもなく、純粋に子供のためのルールだった。
満州から幼かった叔父や叔母を引き連れて祖母と共に日本に帰ってきた過去がある。
父はそれなりの歳だったので、祖母と父が家計を支え叔父や叔母を育てた。
それでも父がおらず母も働きに出ており、とても寂しがる叔父や叔母の姿を見てきたそうだ。
時は流れ、私は新卒で入社した会社を退職し後継者として父の会社に入社した。
その頃、結婚して子供が生まれても会社を退職する気のない事務の女性がちらほら出始めた。
幼い頃の叔母や叔父の悲しみを知る父は「平和な世の中であえて子供に寂しい思いをさせる母親とは何事か!子供には母親のまな板を叩く音で目を覚まし、まな板を叩く母親の背中に迎えられ家に帰る権利がある!」と憤激し今のルールを制定した。
時はさらに流れて私が代表、父が会長となり、さらに父が亡くなってからもこのルールは守ってきた。
しかし、私が膵臓がんにより会長に退いて病床に伏している間に後継の甥はこのルールを廃止してしまった。
今ではむしろ「子育てと仕事を両立できる」ことを人材募集の場でアピールしているらしい。
人手が得られて会社は喜ぶ。
働けて社員は喜ぶ。
裏では寂しく泣く子供かな。
帝政期とはその貴族たちによる議員政治の制度を利用して独裁的な権力を行使する仕組みのことだ。
共和政ローマにおいての首長は、独裁を避けるために二人の執政官が選出され元老院をリードする形を取られた。
しかし有事に際しては一人の独裁官が選出される仕組みとなっていた。
国家の存亡(といっても当初はローマ周辺の小さな都市国家だったのだが)の危機にあたって合議していては遅いからだ。
素早く決断して、素早く行動する。
しかし、共和政ローマにおいて常に危惧されていたのは一人の人間が権力を握ることでやがて王政への道を開くことだった。
ということは常にそのようなことを夢想する輩がいたということの反証でもある。
彼はその前時代に独裁官の権力で政敵を粛清したスッラのやり方を見て着想を得た。
スッラは内戦により権力を握ると独裁官となり、自身の政治信条に基づいた元老院の運営体制を築いた後に独裁官を退き元老院へと権力を戻した。
なぜなら元老院による貴族制政治がスッラの理想とするところだったからだ。
彼はその支持層が貴族ではないことから、権力を握るためには元老院による寡頭政治ではなく、より独裁を必要としたからだ。
これは彼自身の野心であると同時に、対立したポンペイウス派に対抗するための手段でもあった。
カエサルはルビコン川を超えてローマに帰還したあと独裁官に就任、その後内戦に勝利したあと、永久の独裁官に就任するところで暗殺された。
元老院派にとって、共和制の原点であり拠点とも言うべき元老院において、ひとつの政体を退けるために暴力が行使されたというのは元老院議員にとって如何に王政に対する忌避感が強かったのかの現れであろう。
これを見ていた後継者のアウグストゥスは、永久の独裁官という地位を求めることはせずに、様々な制度を複合することで実質的な独裁権を得た。